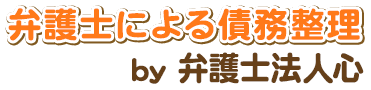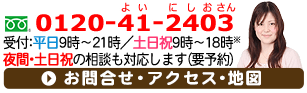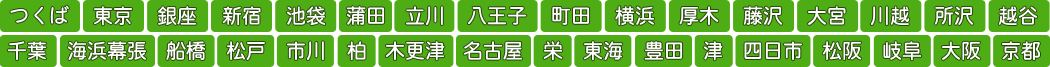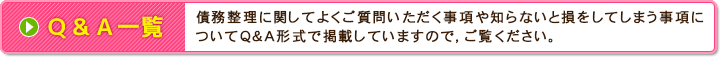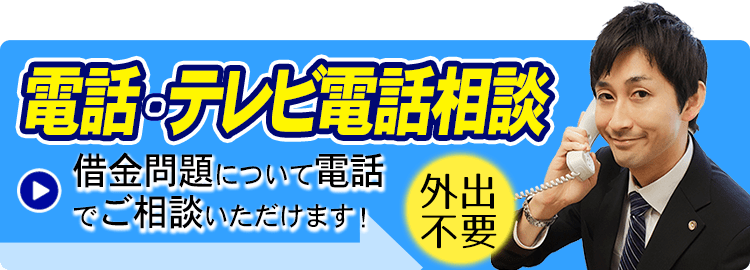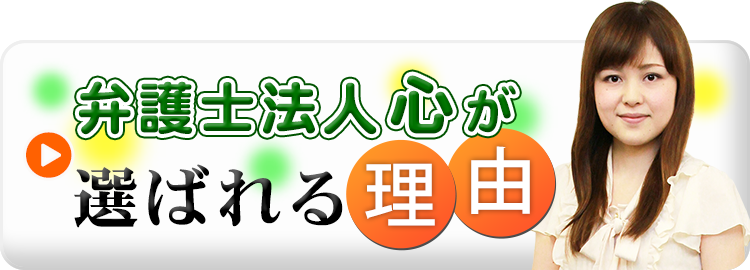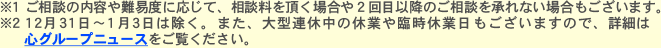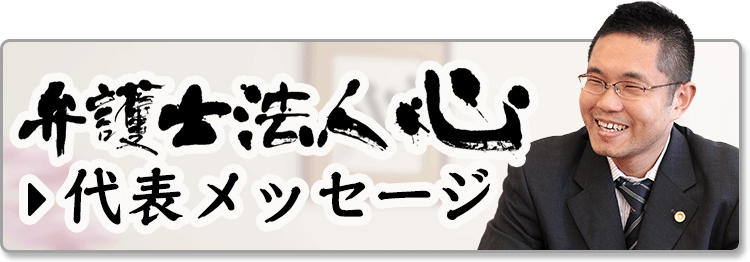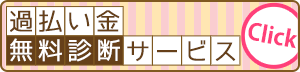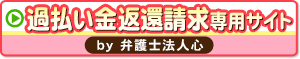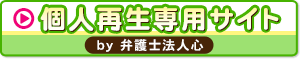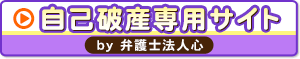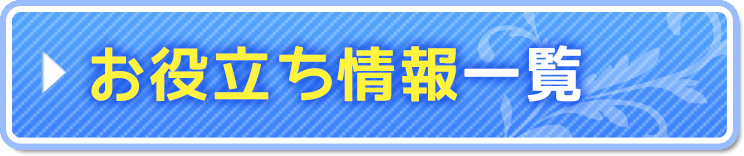「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理と支払督促,裁判
1 支払督促の流れ
⑴ 支払督促とは
支払督促とは、債権者からの申立てに基づいて、簡易裁判所の裁判所書記官が、債務者に対して金銭等の支払いを命じる制度で、民事訴訟法第382条以下に定められています。
裁判を起こして判決を取得するよりも簡単に速く強制執行を可能とする処分をする手続きとなっています。
支払督促の流れは、以下の⑵~⑺のようになります。
それぞれについて、簡単に概要を説明します。
⑵ 金銭などに関する紛争の発生
支払いが滞り、債権者との話し合いがうまく行っていない場合などは、金銭に関する紛争が発生しているといえ、債権者から支払督促の申立てがなされるおそれがあります。
⑶ 債権者による支払督促の申立て
債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申立てがなされます。
参考リンク:参考リンク:裁判所・支払督促
⑷ 支払督促の発付
債権者による支払督促の申立書に不備等がなければ、支払督促が発付されます。
⑸ 支払督促正本の送達
支払督促が発付されると、債務者に対して支払督促正本が送達されます。
⑹ 債権者による仮執行宣言の申立て
債務者が支払督促正本を受領した日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者は、その2週間目の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てをする必要があります。
この期限内に債権者が仮執行宣言の申立てをしなかったときは、発付された支払督促は、効力を失うこととなります。
⑺ 仮執行宣言
債権者による仮執行宣言の申立書に不備等がなければ、支払督促に仮執行宣言が付されます。
仮執行宣言が付されることで、債権者が支払督促を用いて強制執行手続をとることができるようになってしまいます。
⑻ 仮執行宣言付支払督促正本の送達
仮執行宣言が発付されますと、裁判所から仮執行宣言付支払督促正本が送達されます。
⑼ 確定
債務者が、仮執行宣言付支払督促正本を受領した日から2週間以内に仮執行宣言後の督促異議申立てをしないときは、仮執行宣言付支払督促が確定いたします。
⑽ 強制執行の申立て
仮執行宣言付支払督促正本を受領した後も、債務者が任意に支払わない場合、債権者は債務者に対して強制執行手続をとることができます。
強制執行の申立てによって、不動産の競売や給与債権の差押えがなされてしまう可能性があります。
2 支払督促を受けた場合の対応
では、債権者から支払督促を受けた場合には、どう対応するべきなのでしょうか。
まず、一般的には、債務者が支払督促を受けた場合は、簡易裁判所から支払督促正本が郵送で自宅に届きます。
その際、支払督促正本が入っている封筒には、督促異議申立書が同封されているのが通常ですので、督促異議申立書に必要事項を記載して督促異議を申し立てる必要があります。
督促異議を申し立てると、貸金返還請求訴訟という訴訟手続に移行します(訴訟手続の流れについては、3でご説明します)。
支払督促正本を受領してから2週間以内に督促異議の申立てをしないと、支払督促に仮執行宣言が付されて、直ちに強制執行を受ける場合がありますので、注意が必要です。
3 裁判の流れ(貸金返還請求訴訟)
⑴ 訴状・口頭弁論期日呼出状を受け取る
債権者から貸金返還請求訴訟を提起された場合、一般的には、訴状及び期日呼出状が債務者の自宅に郵送されます。
訴状には、通常、債権者の氏名や会社名、債務者の氏名、請求金額、請求を根拠づける契約の内容等が記載されています。
⑵ 答弁書を提出する
訴状には、答弁書が同封されていますので、必要事項を記載のうえ、返送する必要があります。
訴状と同封の口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状には、第1回口頭弁論期日と答弁書の提出期限が記載されています。
一般的には、訴状を受領した日から約1か月程度経過した日に第1回口頭弁論期日が、第1回口頭弁論期日の2週間程度前に答弁書を裁判所に提出する期限が定められていることが多いですが、違うスケジュールとなっている場合もありますので、よく確認する必要があります。
答弁書を提出せず、裁判にも出頭しないと、基本的には債権者の中兆を全面的に認める形で判決が下されることになります。
⑶ 第1回口頭弁論期日
第1回口頭弁論期日は、その裁判で裁判所に最初に出頭する日として期日呼出状に定められています。
ただし、答弁書を提出した場合は、第1回口頭弁論期日を欠席したとしても、裁判所は、擬制陳述といって、答弁書に記載した事項を陳述したものとみなしますので、裁判所に出頭する必要はありません。
なお、簡易裁判所での裁判の場合は、2回目以降の口頭弁論期日であっても、裁判所に対して「準備書面」という口頭弁論期日に先立って弁論の内容を相手方に予告する書面を提出することで擬制陳述という扱いとなります。
⑷ 和解
債務者が、債権者の言い分を認めるものの、一括では支払うことができず、分割払いをしたいという意向があり、債権者がこれに応じるときは、和解がなされることになりますが、この場合は原則として債務者が裁判所に出頭する必要があります。
簡易裁判所で裁判が行われている場合は、和解に代わる決定がなされることも多いです。
これは、債務者が、債権者の言い分を争わない場合に、裁判所が債務者の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときに、分割払いの定め等をすることができるというもので、債務者が裁判所に出頭しなくとも決定が下されます。
⑸ 判決
和解が成立する見込みがなく、両当事者の主張が尽くされたと判断されたときには、判決が下され、両当事者に判決書が送達されることとなります。
⑹ 上訴
敗訴判決が下され、その判決を不服とするときは、上級裁判所に判断を求めることができます。
これを上訴といいます。
上級裁判所とは、簡易裁判所の判決に対しては地方裁判所、地方裁判所の判決に対しては高等裁判所があたります。
上訴は、原則として、判決書を受領してから2週間以内にする必要があります。
4 支払督促や裁判を放置しておくとどうなるか
支払督促や裁判を起こされたという通知を受け取っても、どうしたらよいか分からないという方がほとんどかと思います。
中には、そのまま放置してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、これらを放置すると、自分の財産に強制執行がかけられるという重大な不利益を受ける可能性があります。
⑴ 支払い督促を放置するとどうなるか
まず、支払督促を放置した場合、仮執行宣言が発付されて、仮執行宣言付支払督促が確定するため、債権者は直ちに債務者の財産に対して強制執行の手続きをとることができる立場になります。
そのため、支払督促を受けた場合には、まずは、支払督促正本を受領した日から2週間以内に督促異議の申立てをして、訴訟手続きに移行させるのが適切です。
⑵ 裁判を放置するとどうなるか
次に、裁判を放置した場合、つまり、訴状を受領しておきながら答弁書を提出せず、第1回口頭弁論期日にも欠席した場合には、訴状に対して何も反論がないと判断されます。
そのため、基本的には、裁判所は直ちに債権者の請求を認める判決を出すことができ、判決が確定すると債権者は債務者の財産に対して強制執行の手続きをとることができるようになります。
5 裁判を受けた場合の対応
裁判を受けた場合には、まずは早急に弁護士等の専門家に相談するのが適切ですが、相談日までに答弁書提出期限等が間に合わない場合などには、自分で答弁書を裁判所に提出する必要があります。
答弁書の記載においては、訴状に記載された内容に争いがあればその旨を記載し、訴状の内容には争いがなくとも請求された金額を一括して支払うことが困難な場合で、消滅時効が問題にならないときは、分割払いを希望する旨を記載します。
和解を希望する場合は、原則として裁判所に出頭する必要があります。
答弁書を提出せず、第1回口頭弁論期日に出頭しなかった場合、債権者の主張する内容を認めたとみなされ、債権者の請求を認める判決が下されてしまいます。
6 任意整理中に支払督促や裁判を起こされた場合
任意整理中であっても、支払督促や裁判を起こされる可能性があります。
しかしながら、そのような場合であっても、もう任意整理ができなくなるとは限りません。
支払督促中や裁判中であっても、長期の分割払いの和解が成立することは珍しいことではありません。
任意整理中に支払督促や裁判を起こされた場合、依頼している弁護士等の専門家が支払督促や裁判に対応することとなり、判決確定までに和解がまとまるよう、任意整理の手続きが進められていくこととなります。
7 支払督促や裁判を放置していた後の任意整理
⑴ 任意整理における和解の条件が厳しくなる可能性
支払督促や裁判を放置していた場合、仮執行宣言付支払督促や判決が下されて確定するという事態に陥ってしまいます。
そのような場合、任意整理が必ずできなくなるわけではありませんが、和解の条件が厳しくなる可能性があります。
債権者が勤務先を知っている場合や財産の所在を知っている場合、仮執行宣言付支払督促や判決の確定後に、給与の差押え等が可能となり、債権者としては和解せずともお金を回収できますので、任意整理をするハードルは非常に高くなる可能性があります。
⑵ 仮執行宣言付支払督促や判決が確定してから10年が経過しているとき
支払督促や裁判を長期間放置していた場合で、仮執行宣言付支払督促や判決が確定して10年が経過している例を見かけることがあります。
この場合、消滅時効が完成している可能性があります。
消滅時効が完成していた場合、これを主張することによって債務が消滅し、債務を支払う必要がなくなります。
しかし、仮執行宣言付支払督促や判決が確定した時点以降に、債権者から差押え等の強制執行がかけられていた場合や再度の裁判を起こされていた場合には、消滅時効が完成していたという主張が成功しないことがあります。
また、口頭や書面によって債権者が主張する借金の存在を認めるような行為をしたことがある場合でも、消滅時効が完成していたという主張が成功しないことがありますので、注意が必要です。
時効が完成しているかどうかについては、弁護士にご確認ください。
クレジットカードと任意整理 専業主婦(主夫)が任意整理を行う場合のポイント