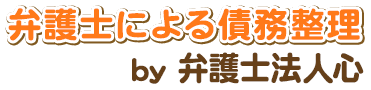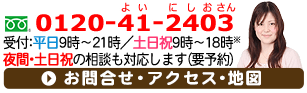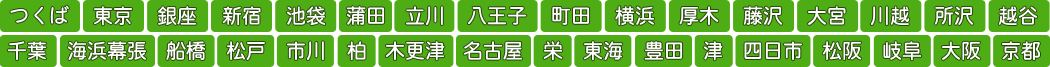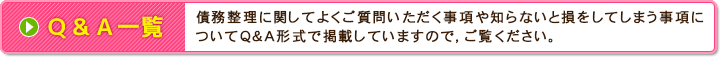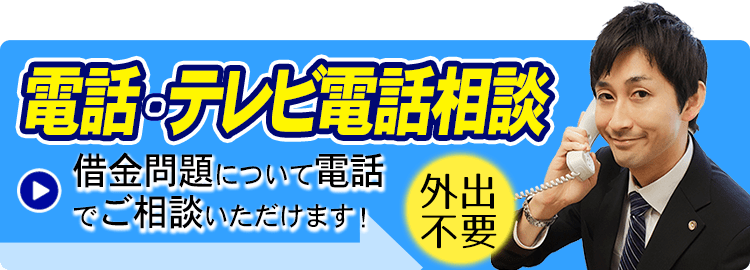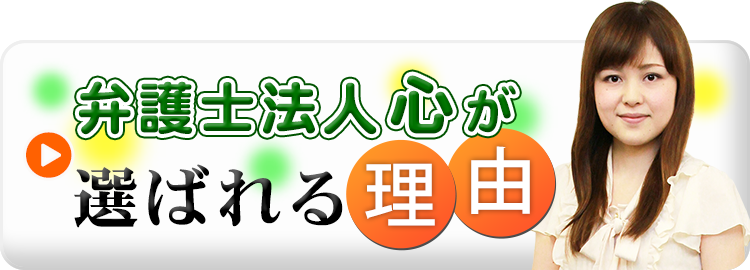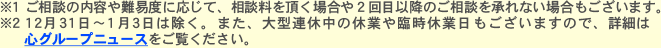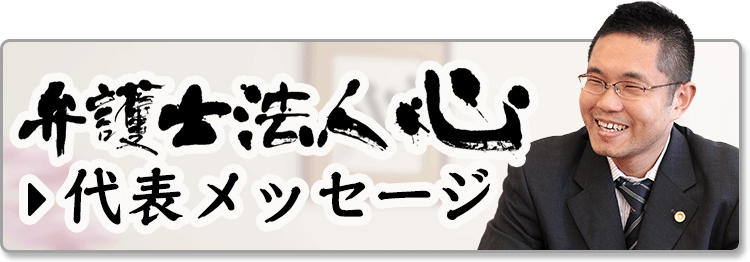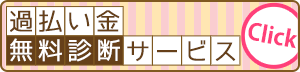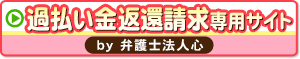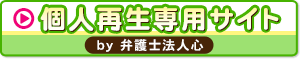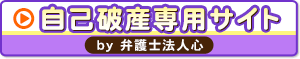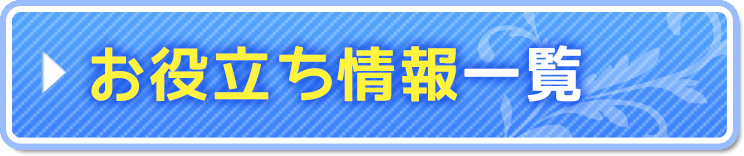「個人再生」に関するお役立ち情報
最低弁済額と清算価値総額について
1 最低弁済額
個人再生では、再生計画を作成し、その内容に従って支払いをしていくことになります。
再生計画によって支払う金額は、最低弁済額以上である必要があります。
最低弁済額は、
① 基準債権総額による計算
② 清算価値
③ 給与所得者等個人再生の場合は、可処分所得の2年分
により決まります。
2 基準債権総額による計算
個人再生では、債務の総額(住宅資金特別条項を定める場合は、住宅ローンを除いた額)から、一定の割合については、最低限支払いをする必要があります。
具体的には、
100万円未満の場合 債務の総額
100万円以上から500万円以下の場合 100万円
500万円以上から1500万円以下の場合 債務の総額の5分の1
1500万円以上から3000万円以下の場合 300万円
3000万円以上から5000万円以下の場合 債務の総額の10分の1
となります。
この金額は、最低限支払う必要があります。
なお、債務の総額が5000万円を超えている場合、個人再生を行うことはできません。
3 清算価値
清算価値とは、簡単に言うと、破産した場合に債権者への支払いに充てられる配当額のことです。
個人再生では、債権者に対し破産した場合より高率の配当を受けされることができるよう、最低限度額は、清算価値以上である必要があるとされています。
そのため、財産等がある場合、住宅ローンがいわゆるオーバーローンの状態になっていない場合には、上記の基準債権総額によって計算した以上の額を支払っていく必要が生じる可能性があります。
4 可処分所得の2年分
小規模個人再生の場合にはこの基準はないのですが、給与所得者等個人再生の場合には、最低限度額は、可処分所得の2年分を下回ることはできないとされています(なお、この基準がない代わりに、小規模個人再生では債権者の過半数の反対がないことが必要になります)。
可処分所得とは、給与所得者の収入から税金等や最低限度の生活を維持するために必要な費用を差し引いた金額によって決まります
この最低限度の生活を維持するために必要な費用は、生活保護の際の基準等により決まります。
5 さいごに
以上、3つの計算された金額のうち、もっとも大きい金額が最低弁済額となります。
多くの方は、基準債権総額による計算方法を利用する可能性が高いです。
ただし、購入して日が浅い普通自動車、解約返戻金が高額な保険、住宅がアンダーローン等で財産が高額になっている場合、清算価値総額(財産の時価の合計)が最低弁済額となる場合があります。
個人再生では、この金額を原則3年、場合によって5年間で支払っていくことになります。
最低弁済額は、個人再生が認められた後に支払う金額ですので、極めて重要になります。
一般の方では判断も難しい内容となりますので、大きな財産を所有している方は、弁護士へご相談ください。
当法人では、毎月2回以上、個人再生を含む債務整理の研究会を開いています。
最新の事例や事務所内での事例・ノウハウの共有を進め、研鑽を重ねています。
個人再生と住宅ローン特則の利用 土木・建設業の個人事業主の個人再生